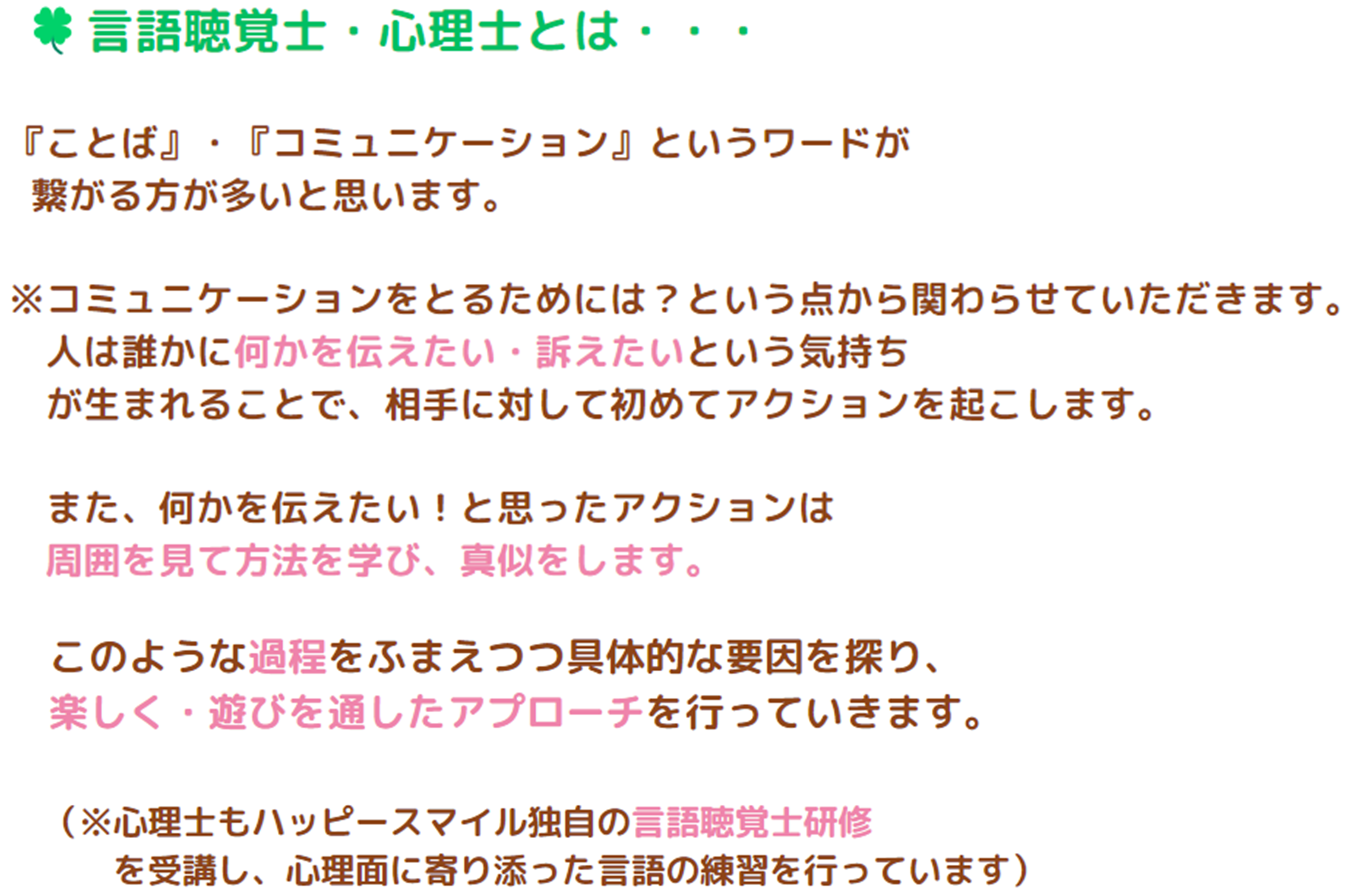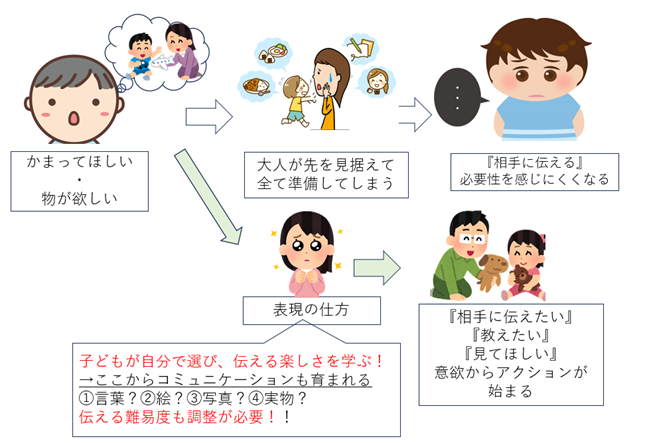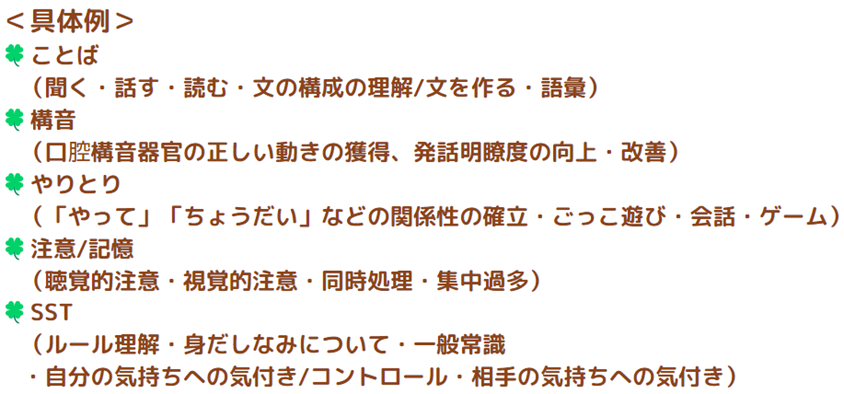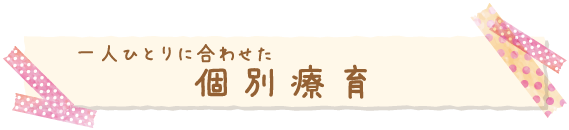
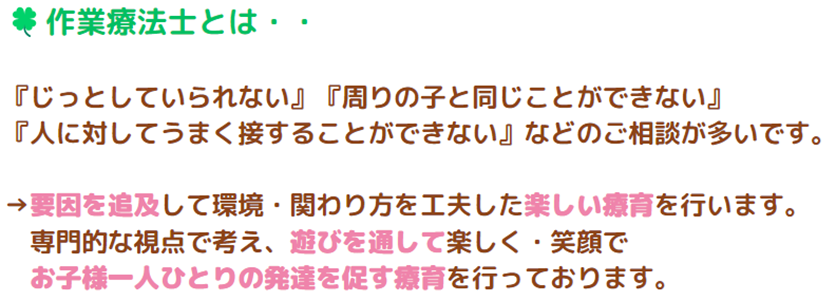
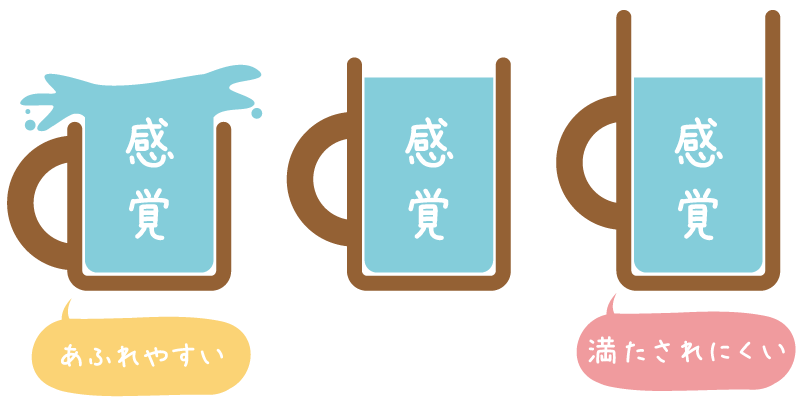
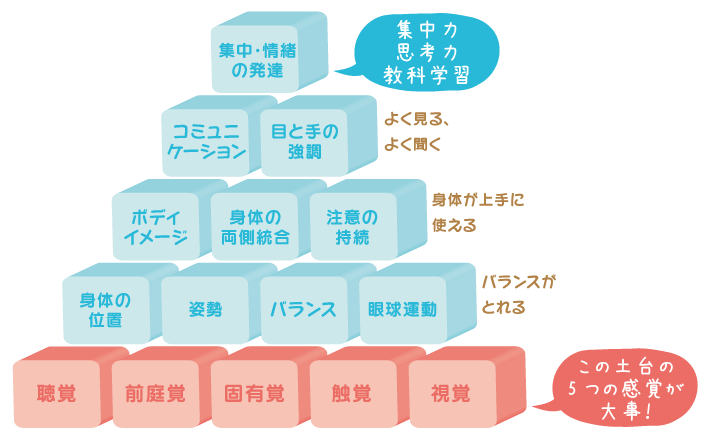
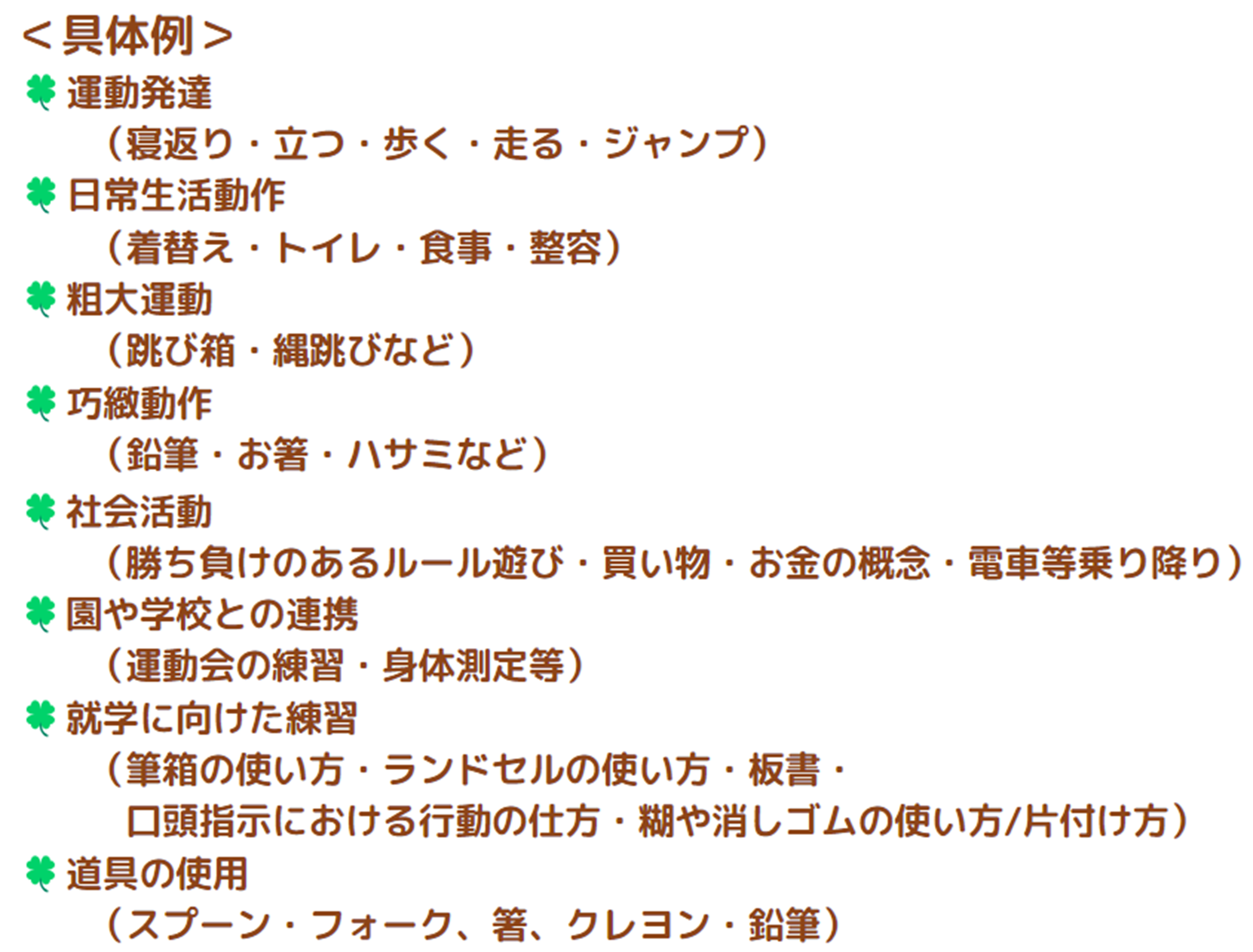

※文献情報:第6回北関東信越ブロック学会・第13回茨城県作業療法学会
論文名:『児童発達支援・放課後等デイサービスでのOTの関わり』
著者名:八代醍 幸恵 (ハッピースマイル津田店 作業療法士)

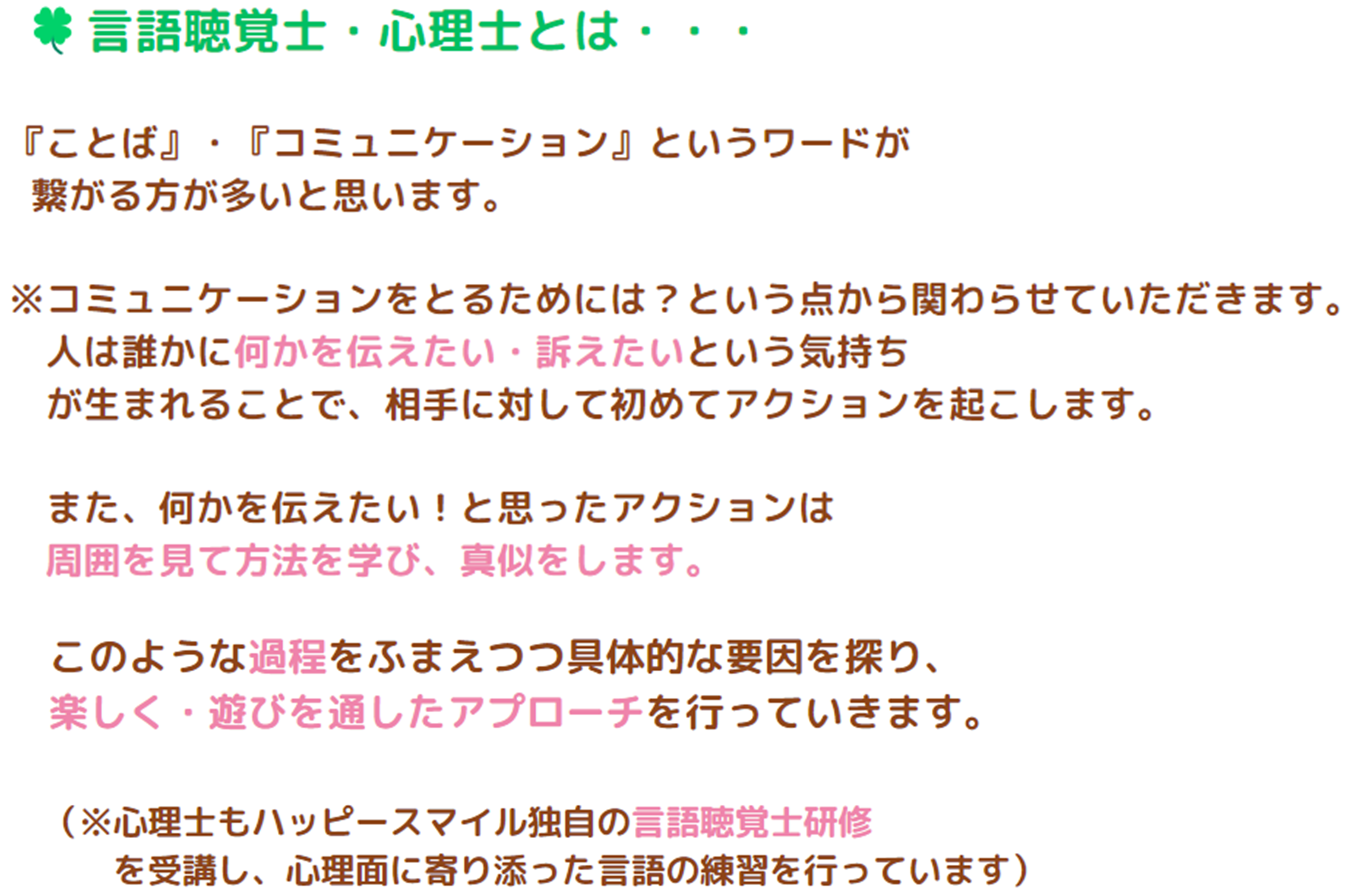
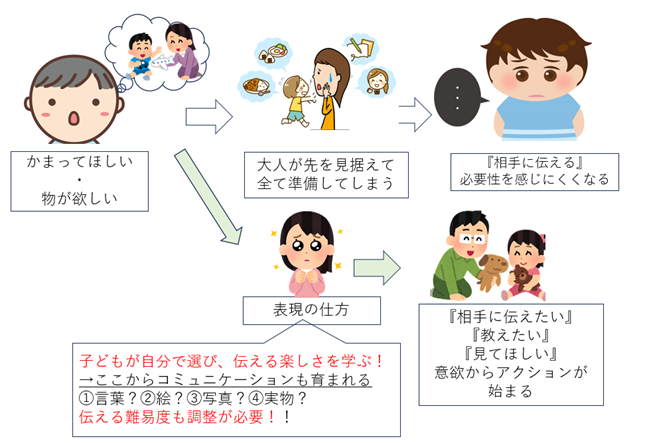
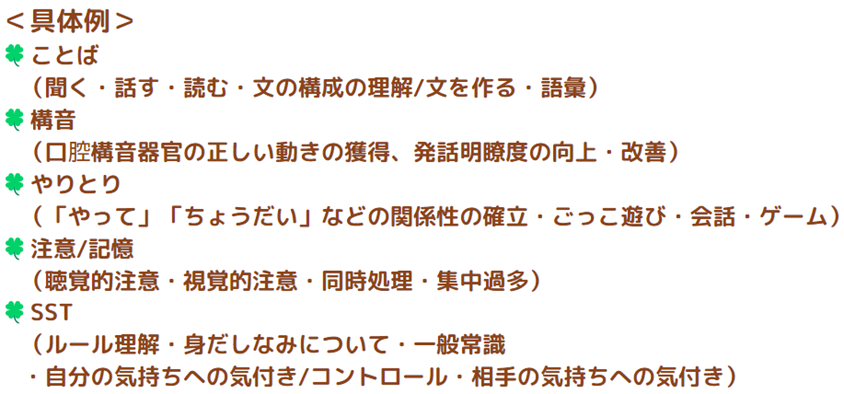





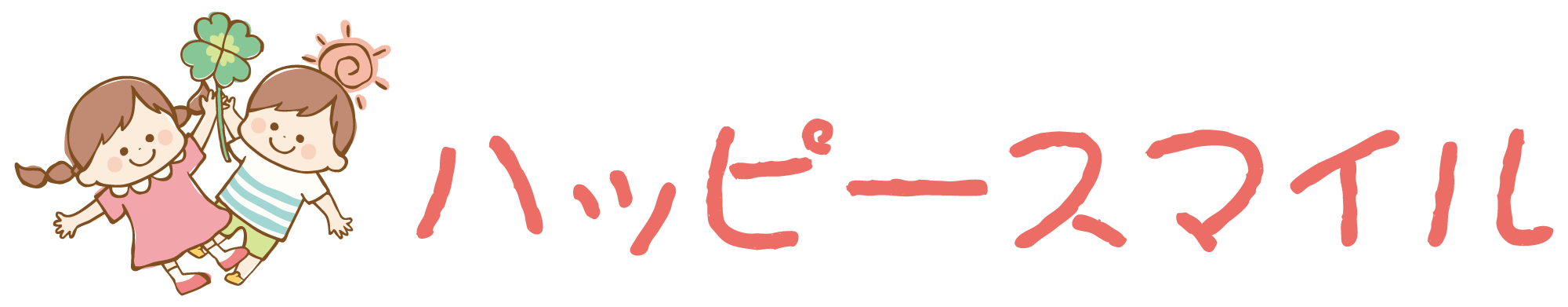
本店 〒312-0041 茨城県ひたちなか市西大島1丁目19-1
TEL 029-229-2295
西大島店 〒312-0041 茨城県ひたちなか市西大島1丁目19-1
TEL 029-219-4702
津田店 〒312-0032 茨城県ひたちなか市大字津田1488-1
TEL 029-219-9124
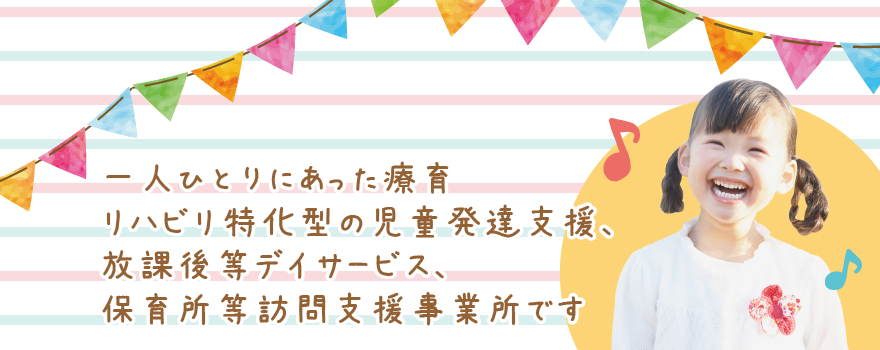
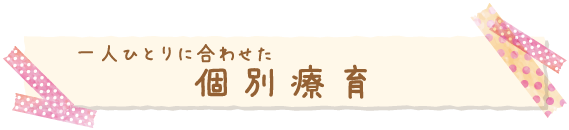
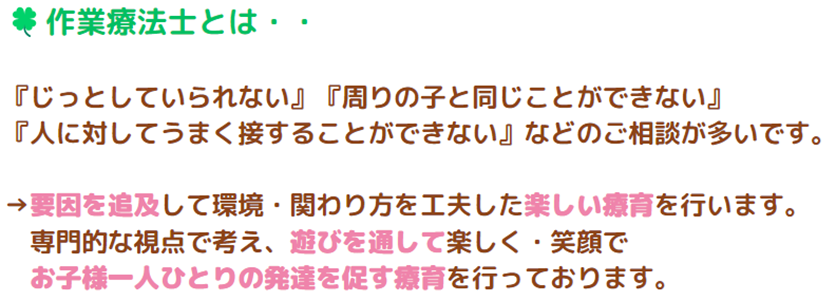
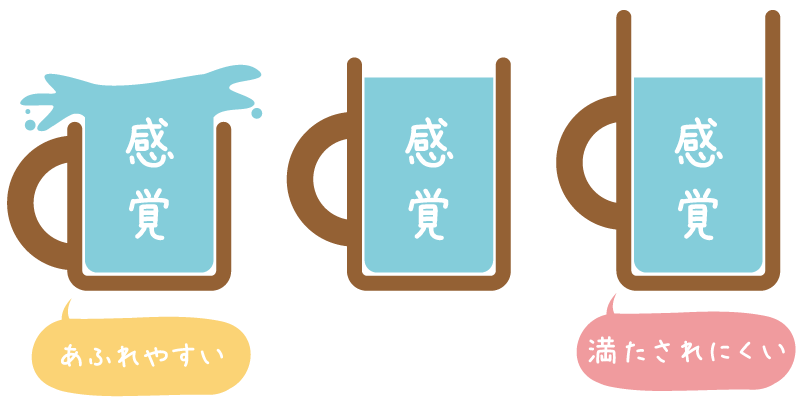
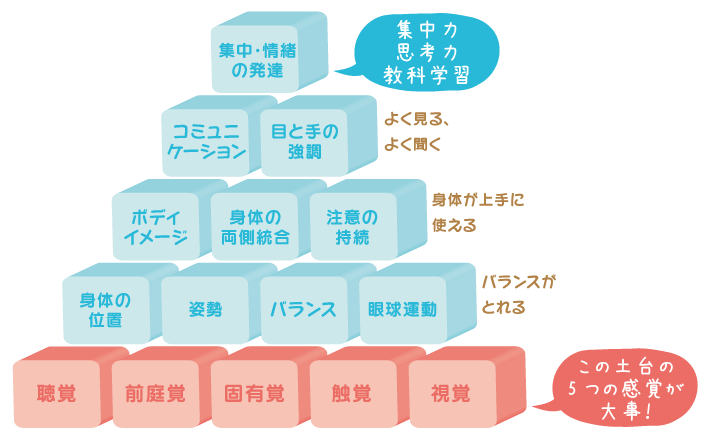
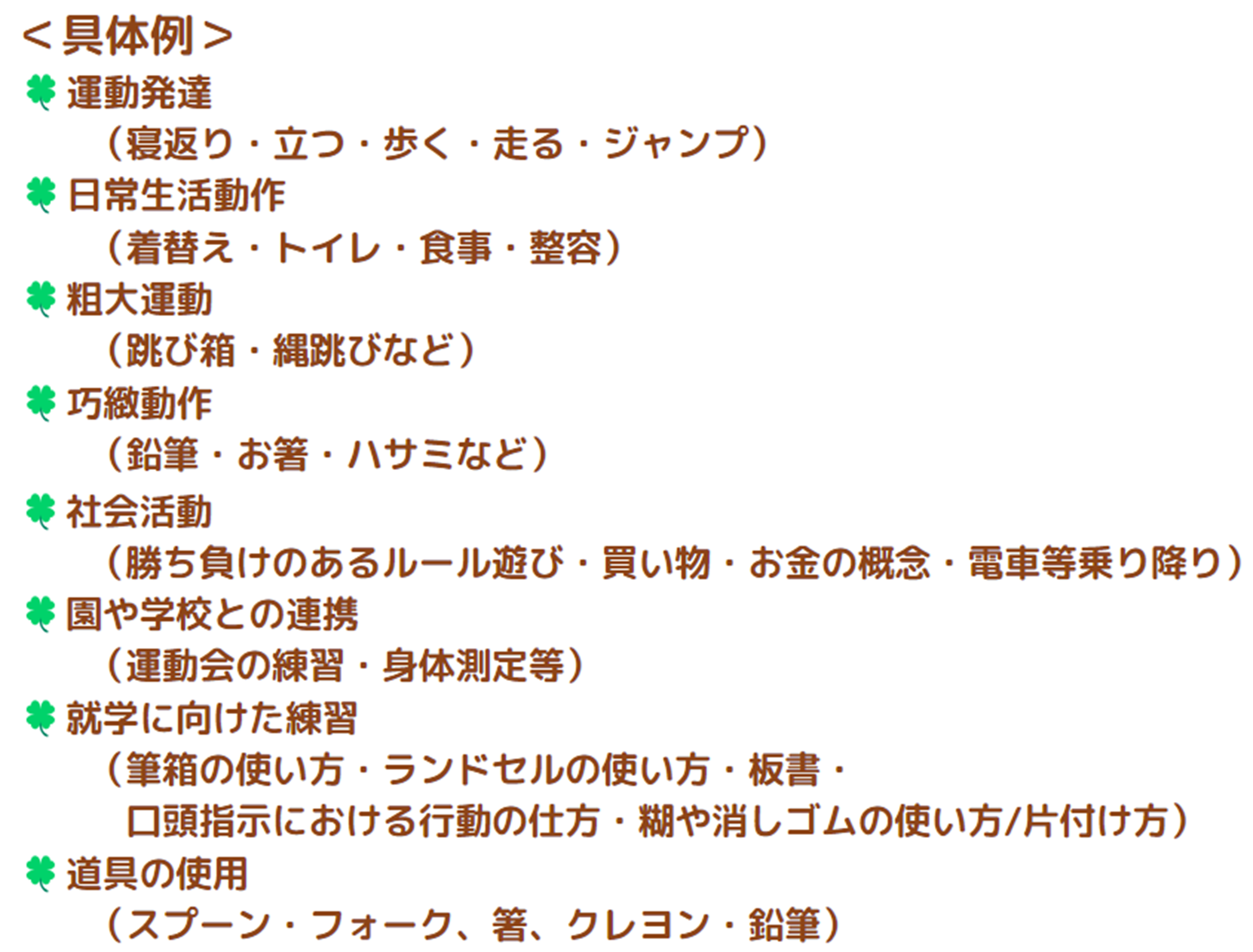

※文献情報:第6回北関東信越ブロック学会・第13回茨城県作業療法学会
論文名:『児童発達支援・放課後等デイサービスでのOTの関わり』
著者名:八代醍 幸恵 (ハッピースマイル津田店 作業療法士)